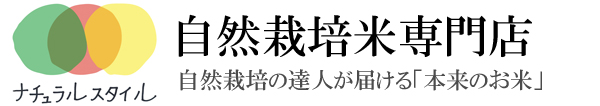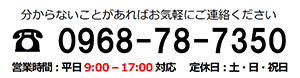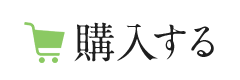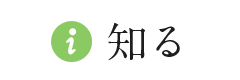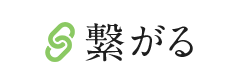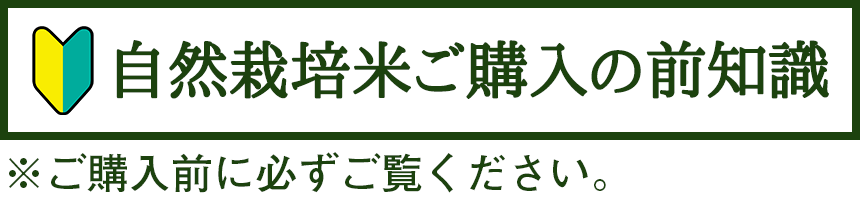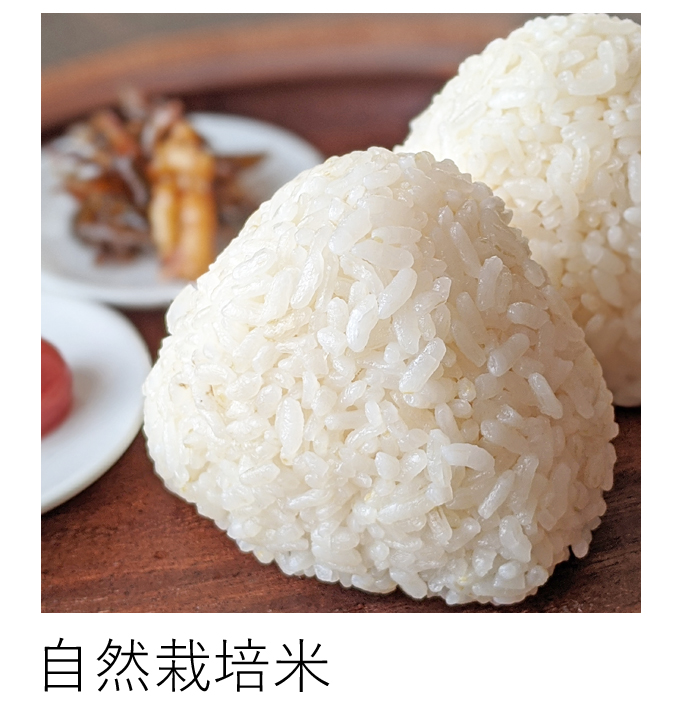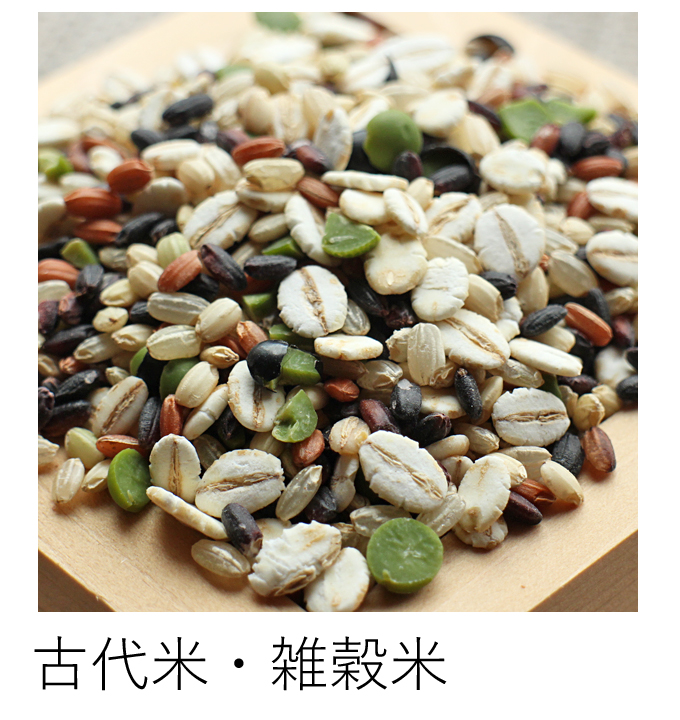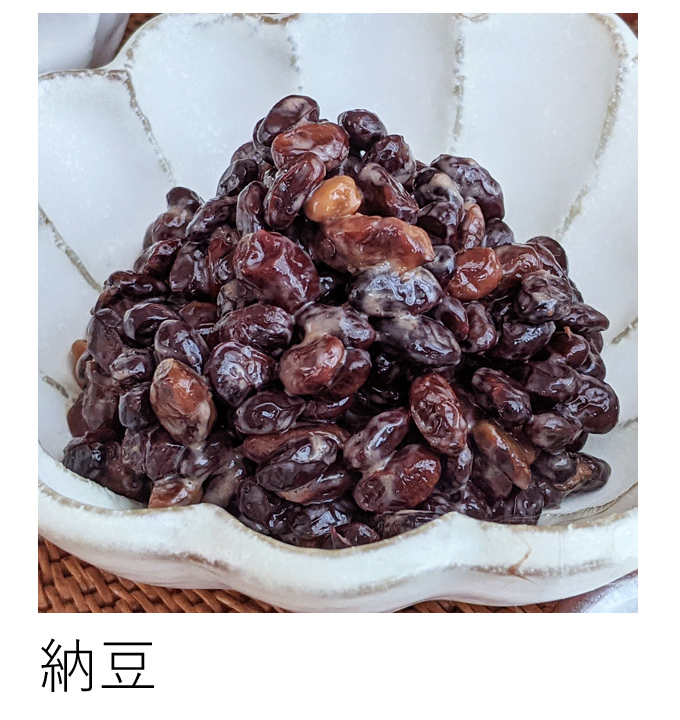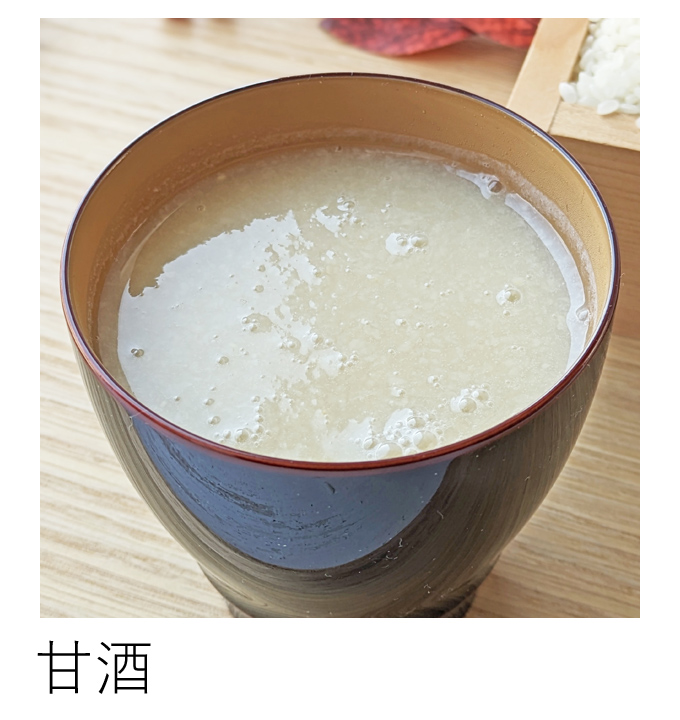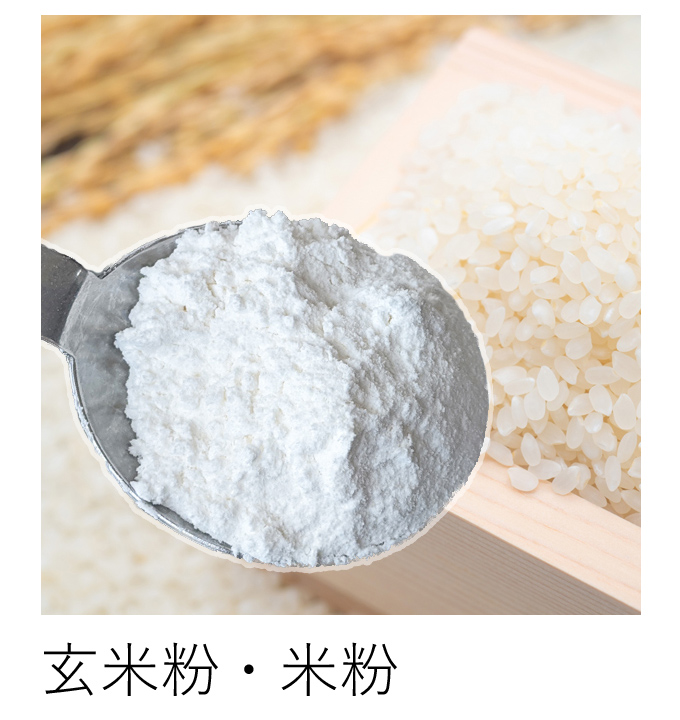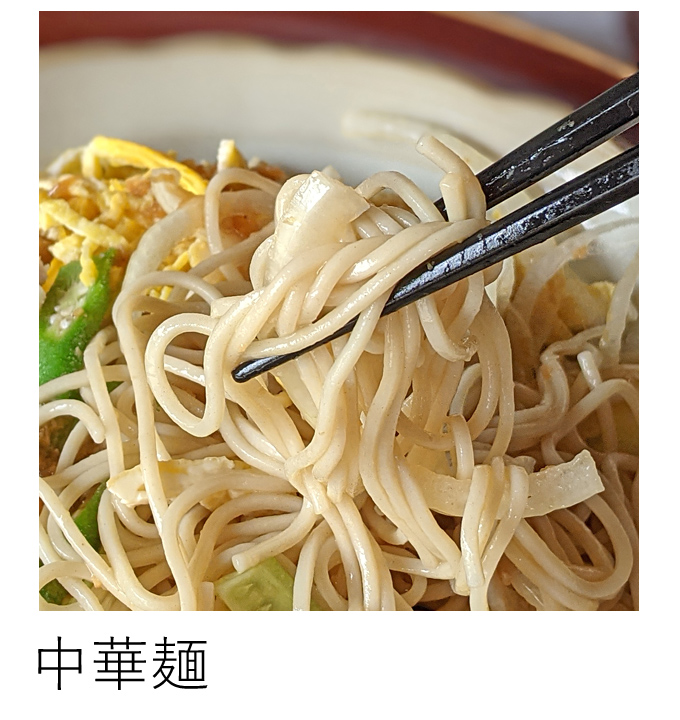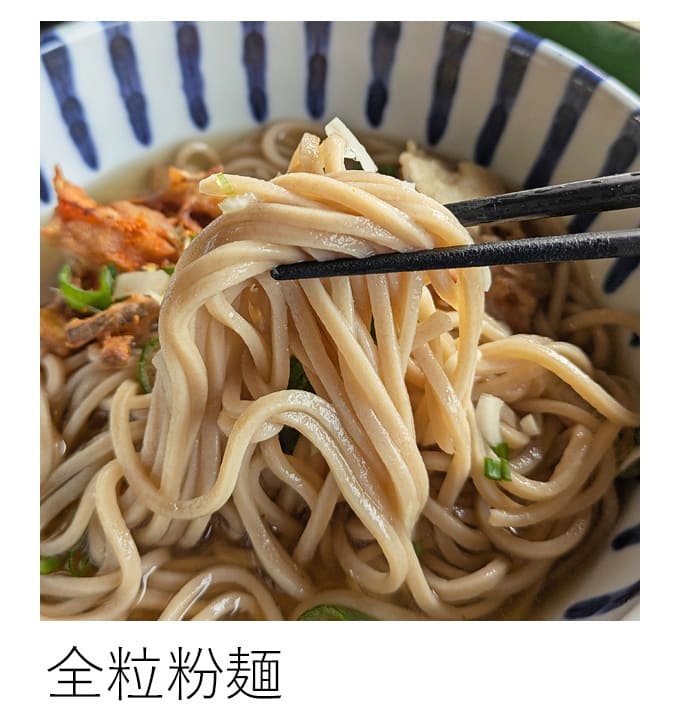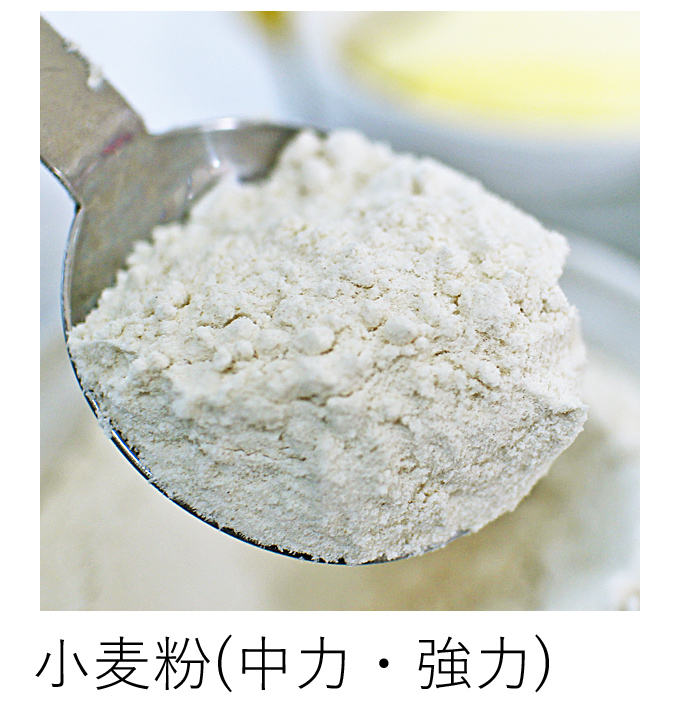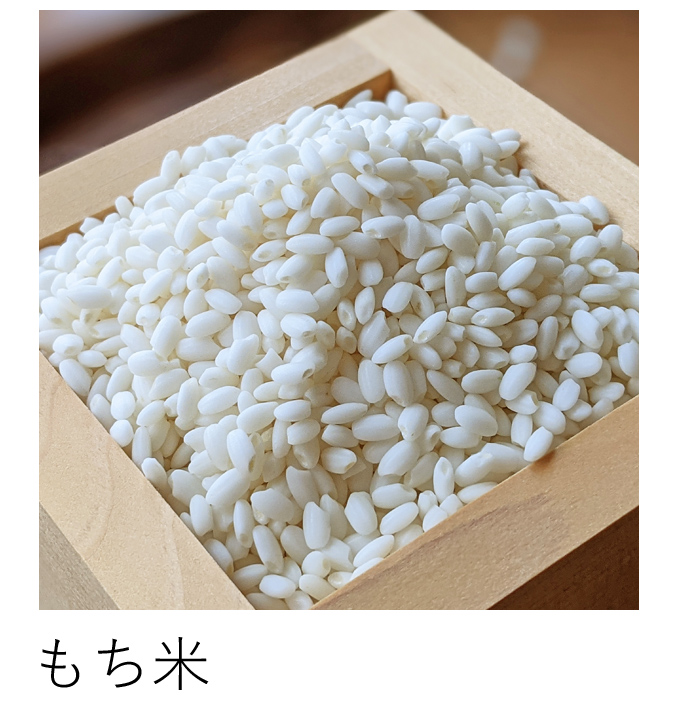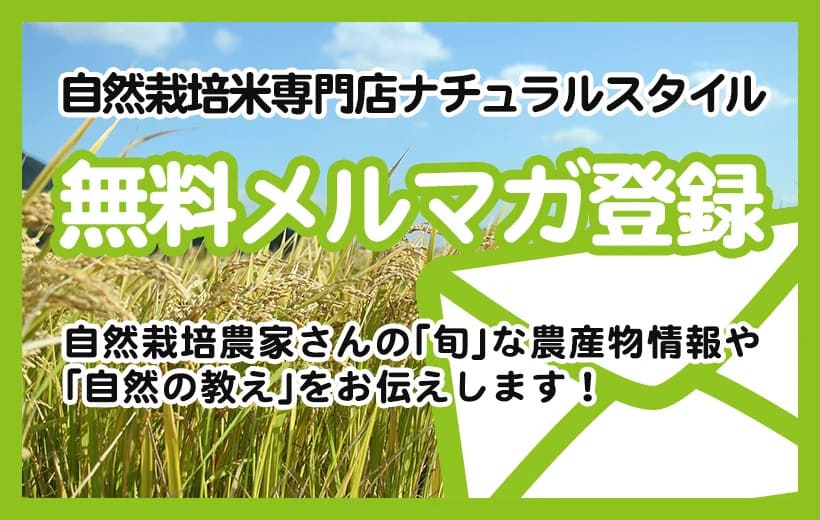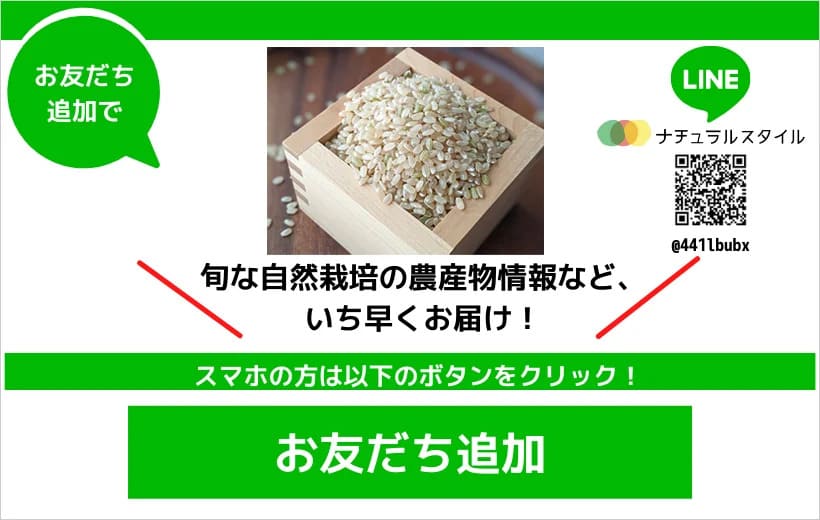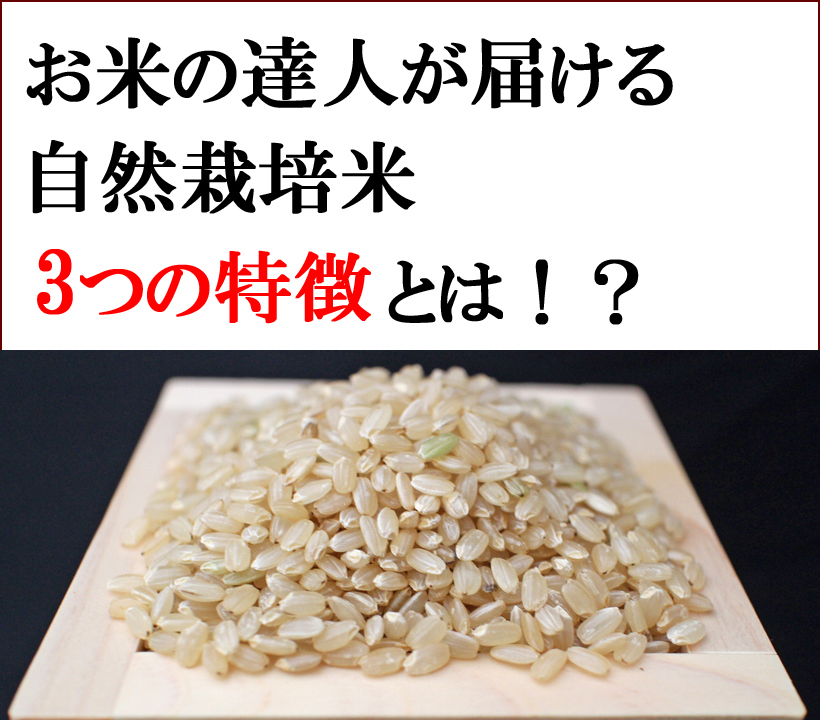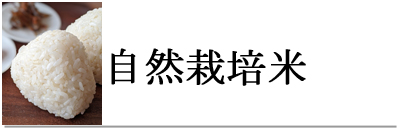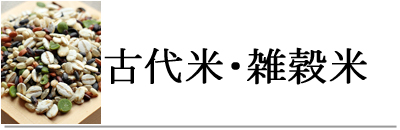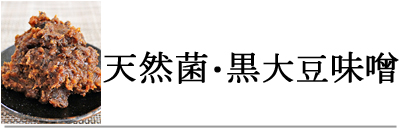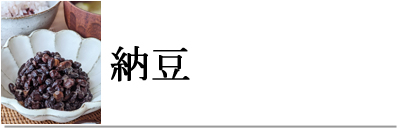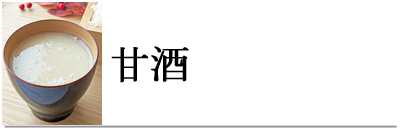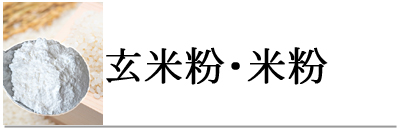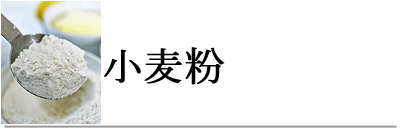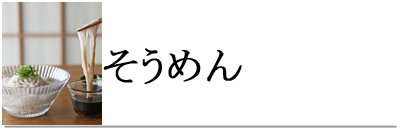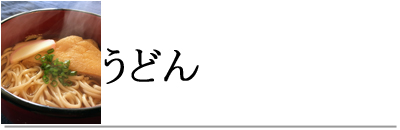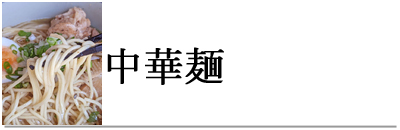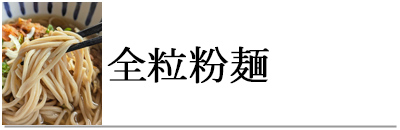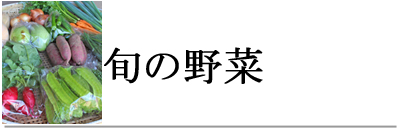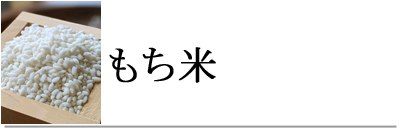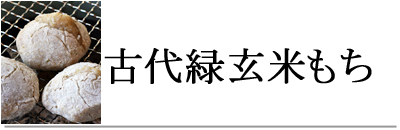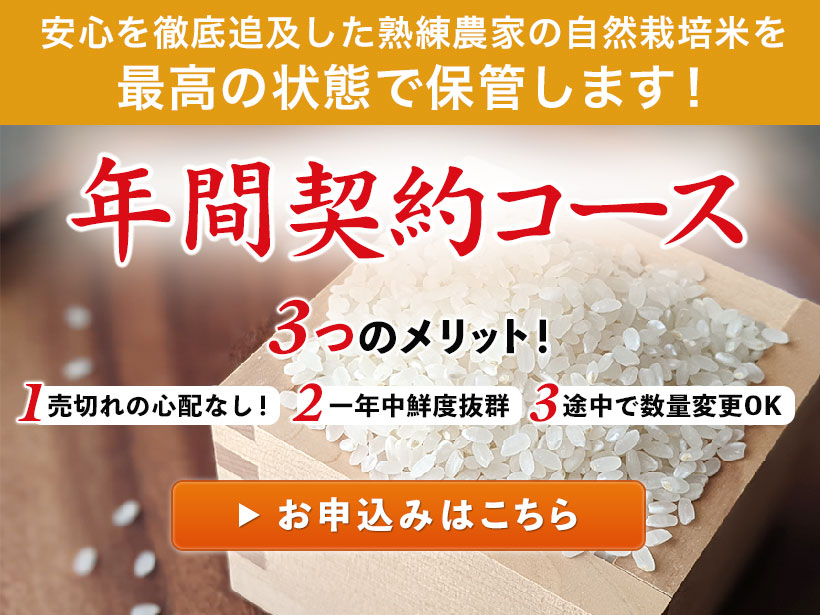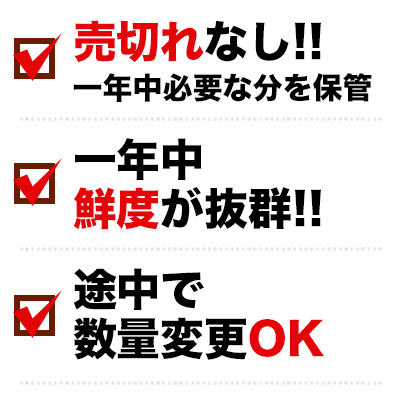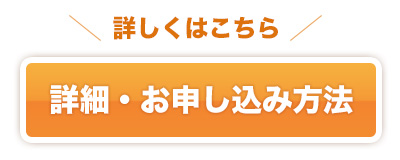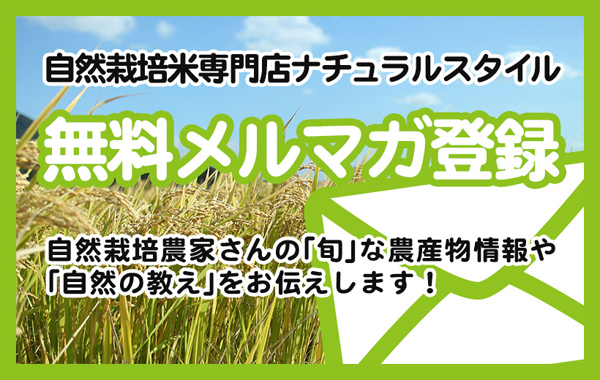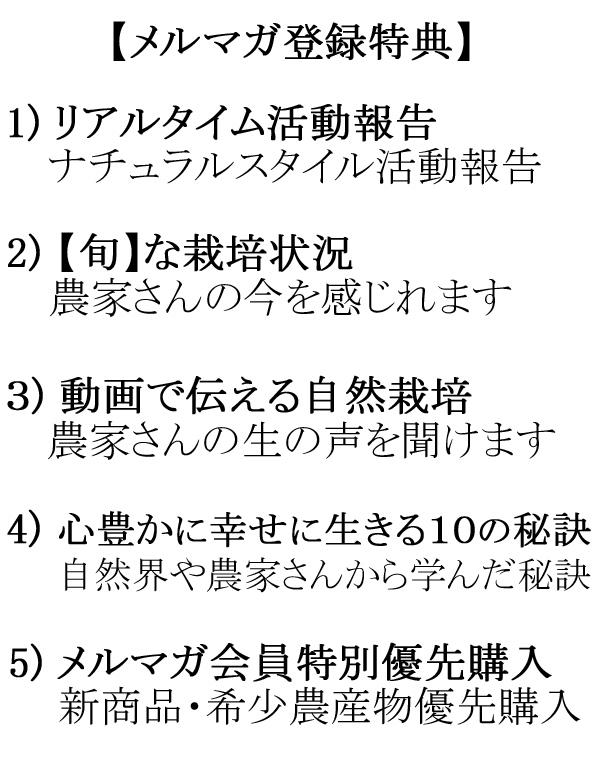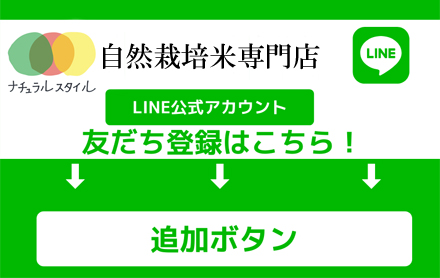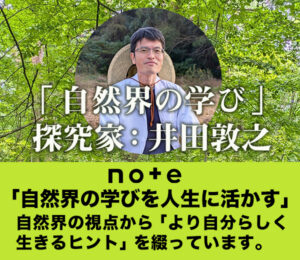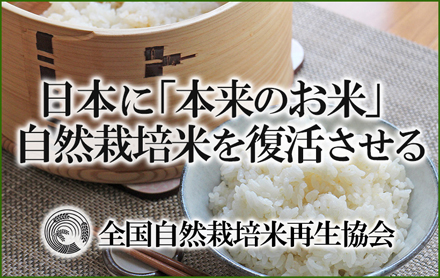有害動物(ジャンボタニシ)の生態を逆手にとった草対策|平田真佐光の自然栽培米

自然栽培米専門店ナチュラルスタイルの井田敦之です。
無農薬・無肥料の自然栽培米作りにおいて、多くの農家を悩ませるのが「草」です。
自然栽培では除草剤を使用しないため、短時間で草をなくすことができません。よって自然栽培米農家は知恵と体力を使い、草と向き合う必要があるのです。
現役の自然栽培米農家は、どのような方法で草対策を行っているのでしょうか。
今回は、熊本県七城町の米農家に生まれ、18歳から無農薬のお米作りに取り組み始めた平田真佐光(ひらた・まさみつ)さんに、どのように草対策をしているのか尋ねました。
目次
自然栽培歴15年以上の平田さんが実践している草対策

自然栽培に限らず一般的な栽培においても、草は大きな問題の一つです。
草は生え過ぎると作物にとって必要な栄養素を吸収するので農作物の収穫量が減ります。そのため、農家は適宜、草対策をする必要があります。
一般的な栽培では除草剤を使い効率的に草を撲滅します。しかし自然栽培では除草剤などを一切使用しません。よって、田植え後1ヶ月間は、チェーン除草や手押し除草機、機械除草機を入れたり、手作業での除草など、労力をかけて草対策を行います。
では、自然栽培歴15年以上の平田さんは、どのように草対策をしているのでしょうか?
平田さんは、すでに田んぼの中に広がっているある動物を草対策に活かしています。
有害動物に指定されたジャンボタニシとは?

平田さんは、有害動物に指定されているジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)を除草に活用しています。
ジャンボタニシは、もともと食用として1981年に台湾から持ち込まれました。しかし食用としての需要はなく、廃棄される過程で野生化し、稲に食害を及ぼす有害動物として日本中に広がってしまいました。
生命力・繁殖力がすさまじいジャンボタニシは、大食漢で植えたばかりの柔らかい苗を食べてしまいます。ジャンボタニシは、農作物に被害を与えるために1984年に有害動物に指定されました。
多くの米農家さんは、ジャンボタニシをいかに排除するのか!と考えます。しかし、排除するために薬剤や資材を田んぼの中に投入すると水田土壌の微生物等が死滅してしまい、自然栽培ではありません。
そこで、平田さんはジャンボタニシの生態を逆手に取って除草に活かしているのです。
ジャンボタニシを活用するメリット

ジャンボタニシを活用することで得られるメリットは、以下2つであると言えます。
1. 農薬に頼らずに除草ができる&省力化にもなる
2.土壌微生物を守ることができる
しかし、ジャンボタニシを野放しにするというわけではありません。油断すると大繁殖し、ほとんどの苗が食べられます。
ジャンボタニシの管理方法
ジャンボタニシは、温度が低い所を好む生物なので、水の深い所を好みます。田んぼに水を入れ過ぎると繁殖が進み、食害も拡大します。
実際に、大雨によって水かさが増した田んぼにジャンボタニシが大発生し、苗をたくさん食べられてしまったという事例があります。
そのためジャンボタニシの繁殖を抑えるために浅水管理が大事になります。
草対策のポイントとは?
ジャンボタニシは、水面が低くなると活動が鈍くなり苗の食害が抑えれます。しかし、水面が低すぎると逆に雑草が繁茂します。
この水面管理は、「ジャンボタニシの苗の食害」と「雑草繁茂」をコントロールするのに重要な作業となっているのです。
ジャンボタニシの食害対策は田植え後1ヵ月が勝負

ジャンボタニシは柔らかい葉を好んで食べるため、稲の苗も大好物です。よって田植え後1ヵ月後は、ジャンボタニシ対策が大事と言っても過言ではありません。
この間、平田さんは田んぼの水を調整し、ジャンボタニシの管理に気を配ります。
上の写真は田植え後1ヶ月の状態です。田んぼの土の上に黒いものが見えます。これがジャンボタニシです。
田植え後1ヵ月経つと稲が強くなるのでジャンボタニシは稲を食べなくなり、今度は稲と稲の間に生えてくる草を食べるようになるので、平田さんにとっては逆にジャンボタニシ=「お世話になる存在」になるのだそうです。
まとめ

自然栽培米農家で最も問題となる「草対策」。今回は自然栽培歴15年以上の平田真佐光さんに草対策に関して伺いました。
平田さんは、既に田んぼに広がっているジャンボタニシを除草してくれる存在として見ていました。
ただジャンボタニシは田植え後1カ月間は植えたばかりの苗を食べるので注意が必要です。その対策として、ジャンボタニシの活動を抑えるために浅水管理が最も有効です。
浅水管理の他には、刈った畔草を水田の際に置いておくこともあります。ジャンボタニシは柔らかい草を好むので刈った畔草に集まってくるので苗の食害を減らすことができます。
1ヵ月以上経てば、苗が強くなっているので、ジャンボタニシは、他の草を食べてくれます。
ジャンボタニシは諸刃の剣ですが、自然栽培農家にとっては大切なお米作りの仲間なのです。
大事なポイントは、今すでに田んぼにいる生物を敵対視のみするのでなく、 共存共栄できる方法はないかと探す姿勢のように思いました。自然栽培米農家さんには、感心するばかりです。
私たち「ナチュラルスタイル」は自然栽培の現状や考え方を広く知ってほしいと思っています。
今回の記事が参考になりましたら、ご自由にこの記事をシェアー下さい。
【参照元】有害動物(ジャンボタニシ)の生態を逆手にとった草対策|平田真佐光の自然栽培米